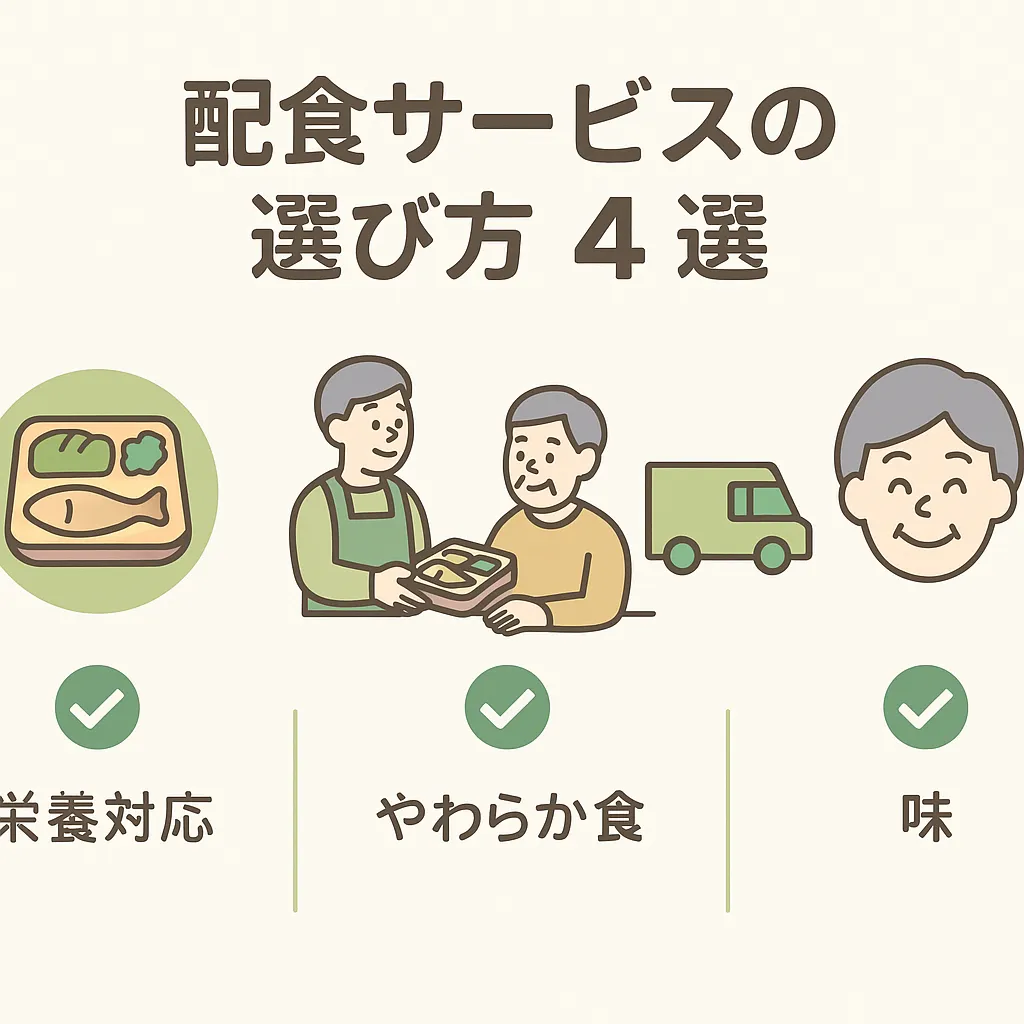離れて暮らすご両親の食事、毎日のことだからこそ心配になりますよね。そんな時、栄養バランスの整った「宅配弁当」はとっても便利ですよ。


この記事では、介護保険が使えなくても費用を抑えられる「自治体の補助金制度」や、あなたにぴったりのサービスを見つけるための「料金だけで判断しないコスパ比較術」まで、分かりやすく解説していきます。
正しい知識を持って賢くサービスを選べば、ご家族の食生活はぐっと豊かで安心なものになります。さあ、一緒に最適な方法を見つけていきましょう!
この記事のポイント
- 宅配弁当は介護保険の対象外
- 自治体の補助金が利用できること
- 自己負担額や料金の計算方法
- 高齢者向け弁当の選び方
介護保険で宅配弁当を頼むための基礎知識

介護保険が使える配食サービスとは?


ご指摘の通り、原則として食事を届けてもらう宅配弁当(配食サービス)は、介護保険の直接の適用対象外となり、料金は全額自己負担となります。
その理由は、介護保険が提供するサービスは、あくまで日常生活を送る上での「最低限の生活支援」を目的としているためです。一方で、調理済みの食事を自宅まで届けてくれる便利な宅配弁当は、生活をより豊かにするための選択肢、つまり「介護保険外サービス」という位置づけになります。
しかし、介護保険の枠組みを使って食事のサポートを受ける方法は存在します。例えば、以下のような関連サービスです。
-
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事の準備や調理、後片付けなどを手伝ってくれるサービスです。これは「生活援助」という介護保険内のサービスに含まれます。- メリット: 利用者の食べたいものや体調に合わせた調理を頼める。
- デメリット: 調理に時間のかかる煮込み料理などは頼めない場合がある。また、あくまで本人のための食事準備に限られ、同居する家族の分までお願いすることはできません。
-
市町村独自の介護保険サービス(市町村特別給付)
すべての自治体ではありませんが、中には独自の制度を設けている場所もあります。
例えば名古屋市では、「生活援助型配食サービス」という市独自のサービスを実施しています。これは、食事代は自己負担ですが、配送料や安否確認にかかる経費(200円)の一部を介護保険でまかなう仕組みです。利用者の負担割合に応じて、20円から60円の自己負担で利用できます。
このように、宅配弁当そのものではなく、調理を手伝ってもらう形や、自治体独自の制度を利用することで、介護保険のサポートを受けられる場合がある、と覚えておくと良いでしょう。
お住まいの市町村にある補助金制度
前述の通り、宅配弁当は原則として介護保険の対象外ですが、がっかりする必要はありません。
実は、多くの市町村が高齢者の食生活を支えるために、独自の補助金(助成)制度を設けています。
なぜなら、自治体にとって高齢者の食事支援は、単なる食事提供以上の大切な意味を持っているからです。
栄養バランスの取れた食事で健康を維持し、低栄養を防ぐことはもちろん、配達員が毎日お弁当を直接手渡しすることで利用者の安否確認を行うという、重要な役割も担っています。
この制度は「高齢者配食サービス」や「食の自立支援事業」など、自治体によって様々な名前で呼ばれていますが、その内容は多くの場合、利用者の経済的負担を軽くするものです。
具体的に、いくつかの市の例を見てみましょう。
| 自治体名 | 対象者(一例) | 自己負担額(一例) | 相談窓口 |
|---|---|---|---|
| 西尾市 | 65歳以上で調理が困難な高齢者など | 配達業者による | 長寿課 高齢者福祉担当 |
| 一宮市 | 65歳以上でひとり暮らし、かつ要介護1~5の方など | 1食330円~570円 | 高年福祉課 在宅福祉グループ |
| 東海市 | 65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方など | 1食300円または480円(所得による) | 担当ケアマネジャー、高齢者支援課 |
このように、利用できる条件や金額は地域によって本当に様々です。
「うちはひとり暮らしではないから対象外かも」と諦める前に、まずは相談することが大切です。
家族が日中仕事で不在になる世帯も対象となる場合がありますからね。
利用を考え始めたら、まずはご自身の担当のケアマネジャーさんや、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」(高齢者の暮らしを支える総合相談窓口)、または市役所の高齢福祉課などに問い合わせてみるのが一番の近道です。
自己負担はいくら?料金の計算方法
宅配弁当を利用する際の自己負担額は、どの制度を使うかによって大きく変わります。
主に3つのパターンがあり、それぞれ料金の考え方が異なります。
パターン1:民間の配食サービスをそのまま利用する(全額自己負担)
最もシンプルな方法で、介護保険や補助金を使わずに、好きな民間の宅配弁当サービスと直接契約します。
- 料金の目安: 1食あたり500円~700円程度が相場です。
これに加えて、業者によっては別途送料がかかる場合もあります。
- メリット: サービスやメニューを自由に選べる。
介護認定の有無に関わらず誰でも利用できる。
- デメリット: 補助がないため、毎日の利用となると経済的な負担が大きくなる可能性があります。
パターン2:お住まいの市町村の補助金制度を利用する
お住まいの自治体の補助金制度を利用する場合、自己負担額を大きく抑えることができます。
- 料金の目安: 1食あたり300円~500円台で利用できるケースが多いでしょう。
- 具体例(東海市の場合): 利用者の世帯の所得状況に応じて、1食あたりの自己負担額が300円、または480円となります。
- 注意点: 利用できる配食事業者が自治体によって決められていることがほとんどです。
パターン3:(例外的)介護保険の仕組みを利用する
これは全国でも珍しいケースですが、名古屋市のように市独自の制度がある場合です。
- 料金の計算方法: 「食事代の実費(全額自己負担)」+「配食経費(200円)の一部負担」という少し特殊な計算になります。
- 自己負担額: 配食経費200円のうち、介護保険の負担割合(1割~3割)に応じて支払います。
- 1割負担の方:食事代 + 20円
- 2割負担の方:食事代 + 40円
- 3割負担の方:食事代 + 60円
どのパターンが最適か、また利用できるかはあなたの状況によって異なります。
だからこそ、まずはケアマネジャーさんなどに相談し、ご自身がどの制度を使えるのかを確認することが、料金を賢く抑えるための第一歩と言えます。
ちなみに、費用を少しでも抑える工夫として、おかずだけを注文してご飯は自分で炊くという方法もあります。
これだけで1食あたり50円ほど安くなることもあるので、検討してみる価値は十分にありますね。
介護保険も考えて選ぶ宅配弁当のコツ
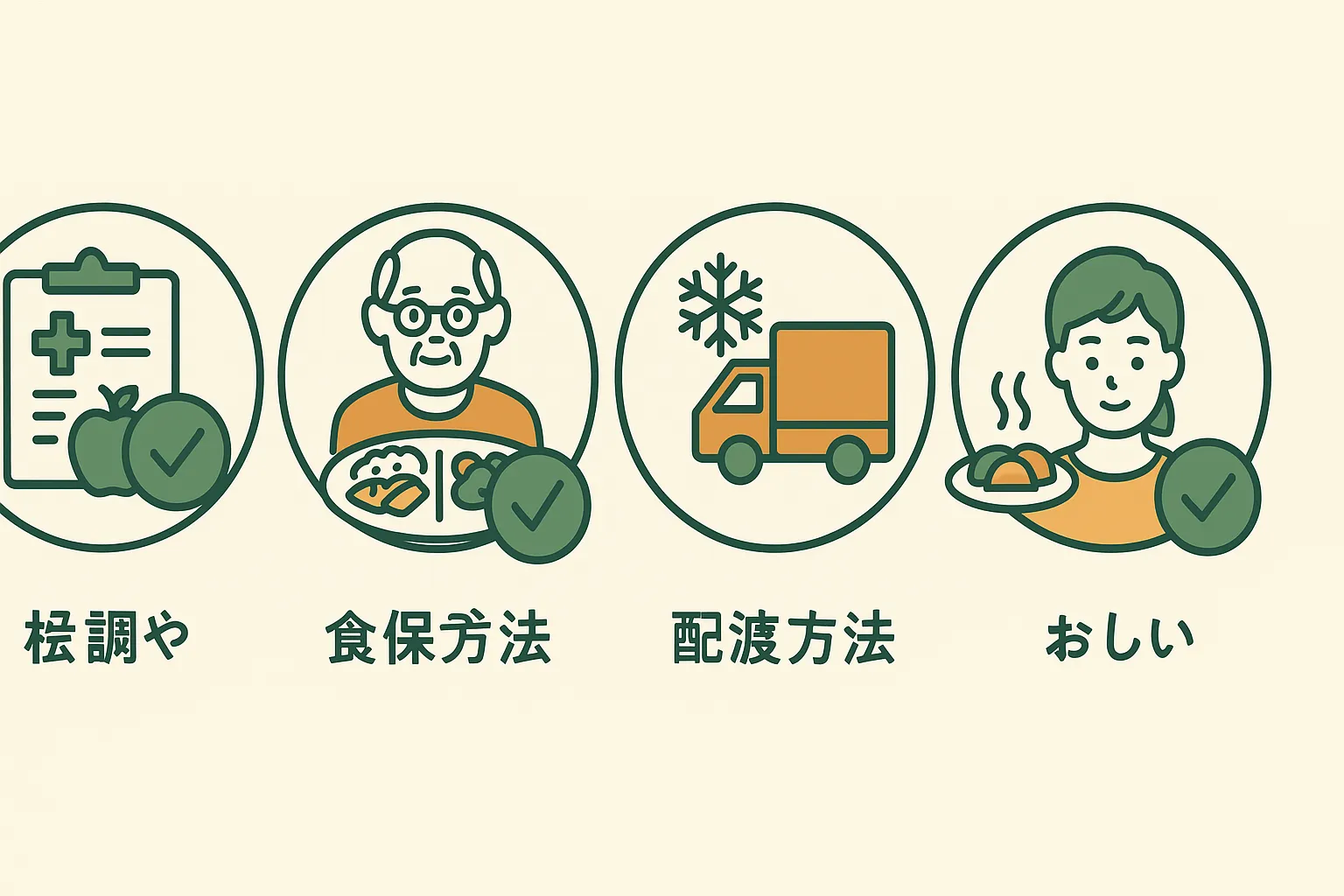
高齢者向けの宅配弁当を選ぶポイント


ここでは、安心して任せられる宅配弁当を見つけるための4つのチェックポイントをご紹介します。
1.体調や持病に合った食事が選べるか
まず確認したいのは、利用する方の健康状態に合わせた食事が用意されているか、という点です。
- 食事制限への対応: 高血圧の方のための「減塩食」や、糖尿病の方向けの「カロリー調整食」、腎臓病に配慮した「たんぱく質調整食」など、専門的な栄養管理がされたメニューがあるかを確認しましょう。「宅配クック123」や「タイヘイ」といったサービスでは、こうした病態に合わせたお弁当が充実しています。
- 専門家の監修: 管理栄養士が献立を監修しているかも、信頼できるサービスを見分ける重要な目印です。栄養バランスがしっかり計算されているため、安心して食事を任せられますね。
2.噛む力・飲み込む力に合っているか
「最近、硬いものが食べにくそう」「むせることが増えた」といった心配はありませんか。これは、噛む力(咀嚼能力)や飲み込む力(嚥下能力)が弱まっているサインかもしれません。
- 食事形態の種類: 普通のお弁当だけでなく、「きざみ食」や「ソフト食」、ペースト状の「ムース食」など、食べやすさに配慮した食事形態を選べるかを確認しましょう。
- 安全への配慮: 例えば「宅配クック123」では、魚の骨を丁寧に取り除いてくれるなど、誤嚥(ごえん:食べ物が誤って気管に入ること)を防ぐためのきめ細やかな工夫がされています。
3.配達方法や生活リズムに合うか
お弁当の届けられ方には、大きく分けて「常温(冷蔵)」と「冷凍」の2種類があり、それぞれに長所と短所があります。
| 配達タイプ | メリット(良い点) | デメリット(注意点) |
|---|---|---|
| 常温・冷蔵 | ・毎日手渡しのため安否確認になる ・届いてすぐに食べられる |
・配達時間に在宅している必要がある ・日持ちしない |
| 冷凍 | ・好きな時に食べられる ・長期保存ができる |
・冷凍庫のスペースが必要 ・毎日の安否確認はできない |
ご本人の生活スタイルや、ご家族が何を重視するかによって、最適なタイプは変わってきます。
4.ご本人が「おいしい」と感じるか
そして何よりも大切なのが、ご本人が食事をおいしく楽しめることです。多くのサービスでは、初めての方限定の「無料試食」や割引価格のお試しセットが用意されています。実際に食べてみて、味付けやメニューが口に合うか、無理なく続けられそうかをご本人に確かめてもらうのが一番でしょう。
料金だけじゃない!コスパで比較しよう
宅配弁当を選ぶとき、どうしても1食あたりの料金に目が行きがちです。
しかし、本当の意味での「コストパフォーマンス(コスパ)」は、単純な安さだけでは測れません。
サービス全体を比較して、ご自身やご家族にとって最も価値のある選択をすることが重要です。
なぜなら、たとえ料金が安くても、味が合わなくて残してしまったり、栄養が偏っていたりしては意味がないからです。
また、食事の準備には、目に見えないたくさんのコストがかかっています。
実際に宅配弁当のコスパを考えるために、3つの視点から比較してみましょう。
1.「1食の値段」の内訳を正しく見る
まず、表示されている料金に何が含まれているかを確認します。
- 食事代: 多くのサービスでは1食あたり500円~700円が目安となります。
- 送料: 冷凍弁当をまとめて宅配便で受け取る場合など、食事代とは別に送料がかかることがあります。
一方で、「ワタミの宅食」のように、表示価格に宅配料が含まれているサービスもあります。
- 入会金など: まれですが、入会金が必要なサービスもあるため、初期費用も確認しておくと安心です。
2.「自炊」にかかる“隠れコスト”と比較する
「やっぱり自炊が一番安いのでは?」と考える方も多いでしょう。
総務省の家計調査によれば、高齢単身世帯の1食あたりの食費は約400円というデータがあります。
しかし、この金額には食材費しか含まれていません。
実際には、
- 光熱費: 調理に使うガスや電気代
- 水道代: 食材や食器を洗う水道代
- 雑費: スポンジや洗剤などの消耗品代
- 時間と労力: 買い出しに行き、献立を考え、調理し、後片付けをする手間
これらの“隠れコスト”を考えると、栄養管理までされた宅配弁当が1食500円台から利用できるのは、非常にコスパが良い選択肢と言えるのではないでしょうか。
3.お金では買えない「安心」という価値
特に、毎日手渡しで届けてくれる常温タイプの宅配弁当には、料金以上の大きな価値があります。
それが「安否確認」です。
配達員が毎日顔を合わせることで、利用者の体調の変化に気づくきっかけになります。
ある方の体験談では、熱中症で体調を崩していた時に配達員の方が気づき、ご家族やケアマネジャーに連絡してくれて助かった、という声も寄せられています。
離れて暮らすご家族にとって、この「安心感」は何物にも代えがたい価値になりますね。
このように、表面的な料金だけでなく、サービス全体の内容や、それによって得られる時間・安心といった価値を総合的に見て判断することが、満足のいく選択につながります。
宅配弁当と介護保険の賢い関係|知らないと損する3つの費用節約術とは?:まとめ
Q&Aでまとめますね。
質問(Q):食事の宅配サービスに、公的な医療保険は使えますか?
回答(A):原則として使えませんが、訪問介護や自治体独自の制度で支援を受けられる場合があります。
質問(Q):費用を安くする方法は、他に何かありますか?
回答(A):多くの市町村に高齢者向けの食事宅配への補助金制度があり、安否確認も兼ねています。
質問(Q):実際に支払う金額は、どのくらいになりますか?
回答(A):全額自己負担で500円から、補助金利用で300円台からと、利用する制度で大きく変わります。
質問(Q):サービスを選ぶ時に、一番気をつけることは何ですか?
回答(A):料金だけでなく、健康状態や食べやすさに合った食事か、ご本人が試して決めることが大切です。
質問(Q):コストパフォーマンスが良いサービスはどう見分ければいいですか?
回答(A):料金に加え、調理の手間削減や安否確認といった、お金には代えられない価値も見て判断しましょう。/p>
この記事では、ご高齢の家族のための食事サポートについて、様々な角度から見てきました。最初は「保険は使えるのかな?」という一つの疑問だったかもしれませんが、一人で悩まずに、自治体の制度を調べたり、ご本人に合うサービスをじっくり選んだりすることが大切だと感じていただけたのではないでしょうか。
お金のことだけでなく、毎日の安心も手に入れられるのが、このサービスの大きな魅力ですよ。まずはケアマネジャーさんや地域の窓口に相談してみるのが、最適な方法を見つける一番の近道でしょう。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。